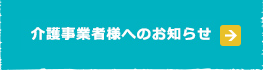最近では介護という言葉を聞かない日がないくらい一般的になりました。私が介護にかかわったのは昭和58年の春、まだ“介護”という言葉もなく、“お世話”と言っていました。テキストもないまま目の前の高齢者に直接かかわり、体験を通して学ばせていただきました。振り返ってみると、日々学びの連続でした。
この連載では主に、在宅で体験した有形無形の学びを伝えていこうと思っています。
施設勤務から在宅に異動して、初めて利用者宅への訪問日を迎えました。利用者宅までの道順を何度も頭の中に描き、時間に遅れないよう、早すぎてもいけないし、道路状況を見ながらの運転です。少し時間が早かったので、利用者宅近くの道路端に車を止め、車内で待っていました。
時間になり、利用者宅の呼び鈴を緊張しながら押すと、少し間があってから、小さな声が返ってきました。ドアを開けてもらい中に入ると、一人暮らしをされている高齢の方で、緊張しているような様子でした。玄関は靴や新聞、日用品でいっぱいです。訪問の趣旨を説明し、居間に通していただきました。テーブルの上は食べ物や書類などでいっぱい、部屋の中は物でいっぱい、長年生活してくると物が増えてしまうし、思い出もいっぱい詰まってくるのでしょう。
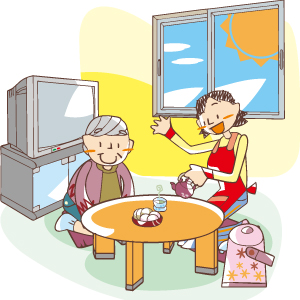
高齢になり、身体状態が低下して日常生活に不都合が生じ、掃除、調理、洗濯などの援助が必要になっての利用です。生活状況を聞き、間取りや物品の位置確認をさせていただくことになりました。緊張しながらも、客観的に生活状況を確認しないとヘルパーさんが困ってしまうと思い、部屋の中や浴室、トイレ、台所などを見させていただきました。冷蔵庫の音が気になったので、「開けていいでしょうか」と聞くと、ためらうように「どうぞ」と言われました。他人の家の冷蔵庫を開けて見ることに多少の戸惑いと躊躇を感じつつ扉を開けると、中は隙間もないほどぎっしりと詰まっており、同時に食べ物が落ちてきました。利用者の方は「あらあら…」と、恥ずかしそうにされていたのが印象に残っています。
私は「これから一緒に、話し合いながらよろしくお願いします」と言いながらも、自分が逆の立場だったらどうだろうと考えました。サービスを利用するということは、自分の生活をさらけ出すことでもあるので、プライバシーや守秘義務の意味が痛いほどに響いてきたのです。サービスを利用する、提供するということは、同じ延長線上にあるのでしょうね。